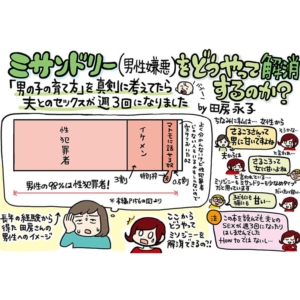うっかりしてしまった“自称ババア”
先日、つい自分を「もうババアだし」と言ってしまった。
最近の健康状態などについて同年代の友達と話していたときのことである。
アラサーと称して差し支えない年齢になり、肌やら胃腸やらが少しずつ変化していくのは煩わしかったり興味深かったりするよね、あそこのサプリがいいらしいよ、といったような世間話を友達としていたのだ。
友達は非常に良いバイブスを持っている人なので即座に「ババアとか言わない」と正してくれたのだが、何より自分自身に驚いてしまった。
「歳を重ねても絶対に“自称ババア”はやらないぞ」と心に誓って生きてきたのに、なぜ……。
「ババア」呼ばわりに甘んじているように見えた先輩たち
“自称ババア”に抵抗を持つようになったのは社会人になってすぐの頃のことだった。社会では新卒の女子社員は当然のごとく「若い女」としての扱いを受ける。
それは「職場の華」的な目の向けられ方であったり、「若い女性ならではの意見を聞かせて欲しい」という、ちゃんと若い女性の意見も聞きますよというただのポーズで実際は聞く気がない=尊重と見せかけたナメられ方であったり、様々な方角から様々なラインナップで表出した。
▼「アンチ女性ならではの感性ステッカ~」created by つっきー(SUZURIで販売中!)
そして少し前まで「若い女」の立ち位置にいた女の先輩たちは、新しく若い女が入ると“ところてん式”にその立ち位置から押し出され、「ババア」のエリアに移動させられた。
若い女から年長者の女まで、さながら「女のナメられ方」見本市のようであった。
同じ部署に女性の年長者がいれば、男性社員はその女性に、「あんまり若い子(私)いじめんなよ〜」と言う(別に全然いじめられてないしむしろ良くしてもらっている場合でも)。
「若い女性の意見を聞かせて欲しい」の段になると、女の先輩に「お前には聞いてないから笑」と言う。
その場にいるみんなが笑う。
こんな無礼が日常の風景としてまかり通っているのがぜんぜん許せなかったけれど、ちゃんと無礼に対して「無礼だぞ」と言えるようになるのはもっと後になってからだった。
新卒の私にとってさらに辛かったのが、そんな扱いを受けている女性の年長者の多くが「ババア」のエリアに甘んじているように見えたことだった。
みんな自分で自分のことを「ババア」とか「おばさん」と言う。
「ババア」と呼ばれたらちょっとおもしろおかしく切り返すのが、1つのフォーマットみたいになっていた。
どうして怒らないんだ、こんなに当たり前のようにバカにされて。こんなに素敵な姉さんたち、尊敬できるところをたくさん持っている人たち(仮に尊敬できるところがなかったとしても)、どうして怒るどころか自分から言うの? と思っていた。
私は怒っていた。
彼女たちにそんな振る舞いをさせる環境が憎かった。
そんなわけで当時の私は「自分は死んでもババアを自称しない」と心に誓った……はずだった。
なのに、自分がいざアラサーに片足を突っ込んだ途端この体たらくである。そしてさらに悲しいのは、「ババア」を自称した瞬間に「不思議な安心感」があったことだった。
この安心感の正体はなに?
散々不満に思っていても、結局私も「若さ」という不毛なレースの中にいて、レースに勝てない年齢になったら「ババア自虐」でひと笑い取れるようになって自分からレースを降りるという一連の動きをしなければ安心できないってことなの?
私はなぜ自分がババアを自称したのかについて、ずっと考えていた。
『あした死ぬには、』塔子の場合
そんな時に出会ったのが、雁須磨子先生の『あした死ぬには、』という漫画である。

映画宣伝会社勤務の多子(さわこ)、パートを始めた主婦の塔子、無職で実家暮らしの沙羅の3人は中学の同級生で、現在は42歳。それぞれの暮らしの中で生じた悩みや不安をオムニバス形式で描いていくシリーズだ(既刊2巻)。
※現在第3話まで期間限定で無料公開中です。
▼URLはこちら
http://webcomic.ohtabooks.com/ashita/
その中で、主婦・塔子にまつわる印象的なエピソードがある。
塔子は23歳で年上の男性と結婚して24歳で子供を産んだ、3人の主要キャラクターの中で唯一の子持ちである。42歳で娘が大学進学で家を出ることになり、さらに夫の海外転勤も決まったため、娘に「パートに出てみれば」と勧められる。
塔子はおっとりした性格で、日々美容に気を配っていて、こまめにフェイシャルパックをしたり体組成計の体年齢を気にしたりしている女性だ。娘もそんな塔子のことを「ママは明るいしかわいいよ」と言ってくれる。
はじめてのパートに出るとあって、塔子はドキドキしながらも美容院へ行って白髪を染めてしっかりキメてから初日に臨んだのであった。
しかし、パート先のレストランでは即座に「髪は帽子の中に全てしまってください」と言われ、ホールは若い子がやるからとバックヤードでの作業を言い渡される。
仕事が終わると髪はぺちゃんこになっていた。
飲食業で髪を帽子にしまわないといけないのは仕方ないこととして、塔子に追い討ちをかけたのは同い年のパート仲間の言葉だった。
「誰もこんなおばさんの頭なんて見てないわよ!!」
「オバさんってもそんな傷つくようなことじゃないと思うんだけど」--。
バイトの若い男の子や娘にフォローされても、塔子のモヤモヤは晴れない。
むしろ余計に死にたくなるのだ。
「私の時代は終わった」「ちゃんとおばさんにならなくちゃ」という塔子の言葉が読んでいるこちらに突き刺さってくる。
結局塔子はパートをやめることはなく、しかしぺちゃんこになった髪を直すためのドライヤーを持っていくようになったところでこの話は終わる。
![]()
“自称ババア”と“おばさん呼ばわりショック”の根っこは同じ
「おばさんになる」って、「美しく歳を重ねる」って、一体なんなのだろうか。
そもそも、みんな1秒ごと歳をとっていくのだから、それ自体は普通にみんなが向かっていくことなのに、「おばさん」という、歳を重ねた女性に対する呼び方には侮蔑のニュアンスがこびりついて取れないのはなぜか。
別に歳をとるのに美しくなくたっていいじゃん、とも思う。そもそも美しさとは何か。
「ババア」を自称して心のどこかで安心してしまった私と、「おばさん」と呼ばれて死にたくなった塔子の、一見正反対に見える2つのしぐさは同根である。
出場した覚えのない「若い女品評会」が勝手に始まることがしょっちゅうな社会で、「私もうババアなんで」と自ら品評会から降りるのは、勝手に出品され、品評され、傷つけられるのを回避するためだ。
言われる前に自分で言って降りた方がましだから。
だからといって他人から「ババア」と呼ばれることを許容したわけでは全くない。
「あなたにはもう出品する価値がないですよ」とジャッジされるのはやっぱり死にたくなるほど傷つくことなのである。
「女の価値=若さ」という重力のなかで生きてきたあとで投げかけられる「ババア」の一言は、たった三音で私を窒息させる。
そんな重力がなくなれば「おばさん」や「ババア」という単語に殺傷能力は無くなり、ただの「年長者の女性」を指す単語になるのかもしれないが、そんな世の中がくるのはまだまだ遠そうだ。
それまでの間、私たちはどうやって生きよう?
自虐をせずに品評会から降りるにはどうしたらいい?
そもそも品評会をまずやめろ、というのは大前提として、私たちには身を守る術が必要だ。
できることはパートにドライヤーを持っていくことくらいの反抗かもしれないけれど、そうやって「ババア」の弾丸から自分の誇りを守っていきたいし、可能な限りその言葉を撃ってくる相手に「無礼だ」と言い返す強さを持っていたい。
誰かが言われていたら、その場で言い返すか、あとで気にかけるなどもしたい。
もし友達がババアを自称していたらなにか言うか、なんと言うかは迷うけれども、できる限り流したくない。
もちろん自分自身に対しても。
そんなわけで、まだまだ「ババア」との攻防は続くのである。
絶対に負けられない戦いだと思っている。